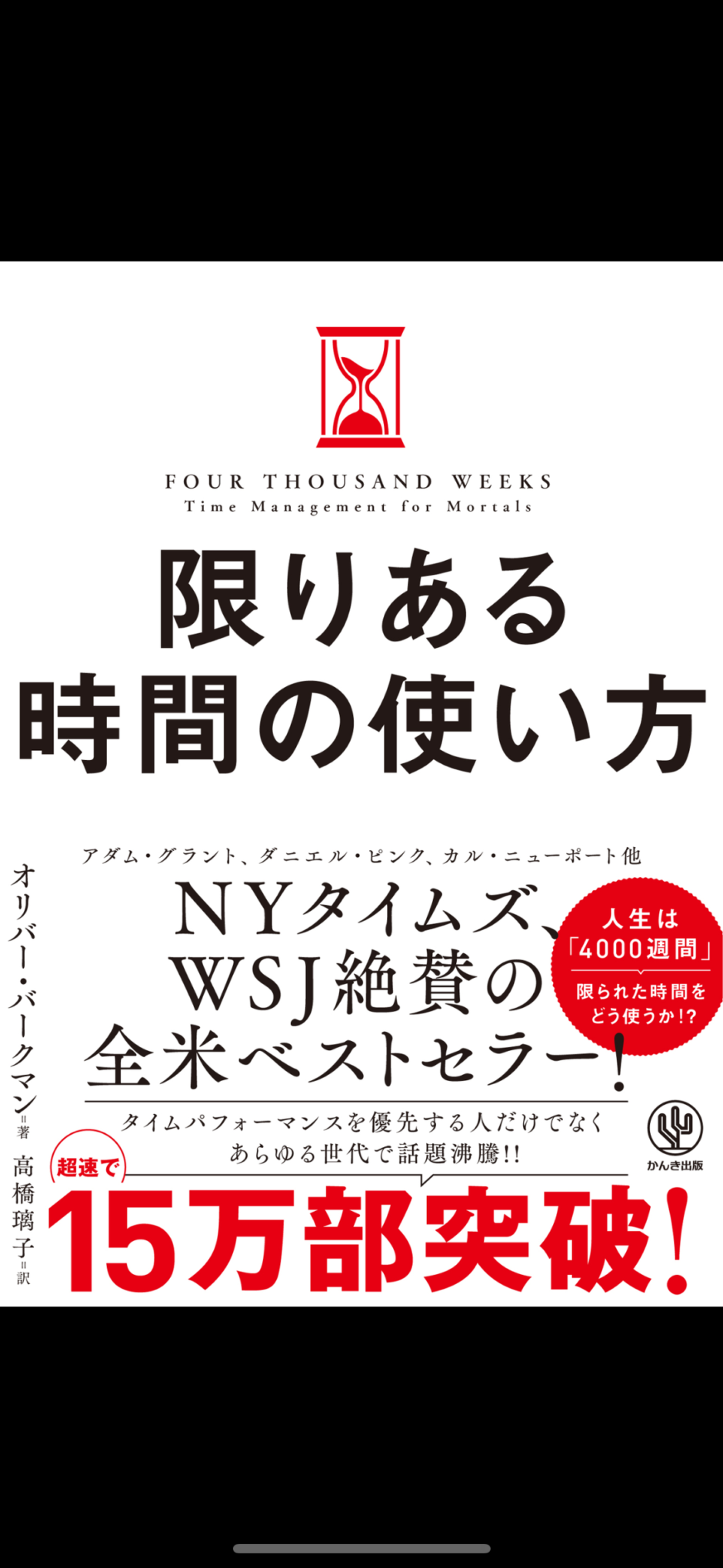「われわれに与えられたこの時間はあまりの速さで過ぎてゆくため、ようやく生きようかと思った頃には、人生が終わってしまうのが常である」
農民の暮らしはけっして楽ではなかった。でも彼らは、日々の暮らしのなかで、神々しく輝く瞬間を知っていた。
作家であり神父でもあるリチャード・ロールはそれを「深い時間を生きる」と表現している。
夕暮れどき、クマやオオカミにまぎれて、森の中でささやく精霊の声。畑を耕しながら、ふと広大な歴史の渦にのみ込まれ、遠い祖先が我が子と同じくらい身近に思えるひととき。作家のゲイリー・エバリーの言葉を借りるなら、「あらゆるものが充分にあり、自分や世界の空虚さを埋めなくていい、そんな領域に突然入り込む5」瞬間。
そんなとき、自分と世界を隔てる境界線は揺らぎ、時間は静止する。
「時計が止まるわけではないが、時を刻む音がふいに聞こえなくなる。」とエバリーは表現する。
祈りや瞑想でそんな境地に達する人もいれば、壮大な風景のなかでふと出会う人もいる。ようやく歩きはじめた僕の息子も、きっと乳児期をそんな状態のなかで過ごしていたのだろう(新生児との最初の数カ月間がなんだか別世界のように感じられるのは、寝不足のせいだけではなく、赤ちゃんによって「深い時間」に引きずり込まれるせいかもしれない)。
スイスの深層心理学者カール・グスタフ・ユングも、1925年にケニアを訪れたとき、夜明け前の平原で時間を超越した感覚に襲われたという。
ム大なサバンナの低い丘を登ると、壮大な風景が目の前に開けた。大地は見渡すかぎり、動物たちの群れに覆われていた。ガゼル、アンテロープ、ヌー、シマウマ、イボイノシシ。草を食み、頭を揺らしながら、川のようにゆったりと進んでいく。猛禽類の哀しげな鳴き声のほかに、ほとんど音はない。それは永遠なる始まりの静けさであり、変わることのない世界であり、無の境地であった。私は仲間の姿が見えなくなるまで歩いていき、完全なる孤独を味わった。
ところが今を犠牲にしつづけると、僕たちは大事なものを失ってしまう。
今を生きることができなくなり、未来のことしか考えられなくなるのだ。
つねに計画がうまくいくかどうかを心配し、何をやっているときも将来のためになるかどうかが頭をよぎる。いつでも効率ばかりを考えて、心が休まる暇はない。あの「深い時間」、時間の物差しを捨ててリアルな現実に飛び込んでいくときの魔法のような感覚は、もうどうやっても手が届かない。
この人生はリハーサルではない。あらゆる選択に無数の犠牲がついてくる。時間はつねにすでに差し迫っていて、今日や明日にも完全に尽きるかもしれない。よくいわれるように「今日が人生最後の日のつもりで」過ごすだけでは足りない。「つもり」ではなく、実際に今この瞬間が人生最後であるかもしれないのだ。未来が一瞬でも残されていると確信することはできない。
普通に考えれば、こういう態度は病的でストレスフルだと思う。でも、人生をそのように見ることができたなら、あなたは普通でない考え方を手に入れたことになる。
それは、少なくともハイデガーによれば、「病的でストレスフル」の対極にある生き方だ。むしろそれは、限りある人生を真摯に生きるための唯一のやり方だといっていい。そうすることで初めて、他の人たちとまっとうな関係を築き、世界をありのままに体験できるのだ。
彼はそれに対比させて、家族や親戚と年に一度集まって過ごす夏休みのことを語る。風の強いスウェーデンの海辺で大切な人たちと過ごす時間が特別なのは、それが永遠には続かないからだ。自分はいつまでも生きるわけではない。家族や親戚も同じだ。そこに集まる人たちの結びつきもまた、一時的なものにすぎない。目の前に広がる海岸線さえ、時間とともに形を変えていく。
もしも夏休みが何度でも無限にやってくるなら、そこに特別な価値はない。無限には続かないからこそ、価値があるのだ。
死が確実にやってくること、そして自分が死に向かっていることを見つめたとき、人はようやく本当の意味で生きることを知るのだ。
癌になった有名人が、きまって闘病体験を「すばらしい出来事だった」と語るのは、まさに人生の有限性に直面するからだ。みずからの死に直面したために、人生の見え方が変わり、あらゆるものが鮮やかな意味を持って立ち上がってくるのだ。
死にかけた人が、それまでよりも幸せになるわけではない。そんな単純な話ではない。自分が死ぬという事実、そして自分の時間がとても限られているという事実を骨の髄まで実感したとき、人生には新たな奥行きが現れる。
幸せというよりも、人生がよりリアルになるのだ。
何かを諦めることはつらいから、何もかもを詰め込みたいと思うのも無理はない。けれど、もしも存在していること自体が当たり前ではないとしたら-銃乱射事件のニュースを見てケインが悟ったように、「人生のすべては借り物の時間」なのだとしたら何かを選択できるということ自体が、すでに奇跡的だと感じられないだろうか。
選べなかった選択肢を惜しむ必要はない。そんなものは、もともと自分のものではなかったのだ。あなたが何を選ぶとしても!家族を養うためにお金を稼ぐ、小説を書く、子どもをお風呂に入れる、ハイキングに出かけて地平線に沈む淡い冬の太陽を眺める-、それはけっしてまちがいではない。
意識しなくても自然に入ってくる情報がなければ、人間は生きていけない。脳科学者はこれを「ボトムアップ型の注意」または「不随意的注意」と呼ぶ。一方、僕たちはある程度まで、意識的に注意をコントロールできる。
「トップダウン型」の注意、つまり自発的な注意力だ。
トップダウン型の注意をうまく使えるかどうかで、人生の質は左右される。
この感動的な事実はしかし、裏を返せば、恐ろしい真実を明らかにする。どんなに恵まれた環境にいても、注意の使い方によっては、何の意味もないみじめな人生を送ってしまうということだ。
意味のある体験をするためには、その体験に注意を向けなくてはならない。注意を向けていないことは、起こっていないのと同じだからだ。
将来のことを考えたり、計画を立てたりするとき、僕たちは「時間を所有したり使ったりできる」という前提に立っている。そしてその前提のせいで、いつもイライラしたり、不安になったりしている。時間は自分のものではないし、自由に使うこともできないという確固とした現実が、つねに僕たちの期待を打ち砕くからだ。
計画を立てるのが悪いことだといっているわけではない。老後のためにお金を貯めたり、期日までに投票に行くのは良いことだ。未来を良くしようという努力には何の問題もない。
本当の問題は、その努力が成功するかどうかを、今この時点で確実に知りたいと思う心理にある。それが不安を生むのだ。
哲学者であり徹底した悲観主義者だったアルトゥール・ショーペンハウアーは、人の欲望の必然的な結果として、このような人生の空虚さは避けられないと考えていた。
こういう論理だ。人はみんな、さまざまな目標を達成しようとして日々を過ごしている。ところで、それぞれの目標は、まだ達成されていないかすでに達成されたかのどちらかである。まだ達成されていなければ、欲望が満たされないので不満である。一方、すでに達成されてしまった場合も、追い求める目標がなくなってしまって不満である。したがって、いずれにせよ、人は不幸なのだ。
ショーペンハウアーは著書『意志と表象としての世界』のなかで、こうしたジレンマを「意志の対象」を持つことの本質的な苦痛として描きだす。手に入らなければ苦痛だ。そして「あまりにも簡単に満足が得られてすぐに意志の対象がなくなってしまうような場合にも、虚しさと退屈がやってくる。ただ人として存在することが耐えがたい重荷となるのである。したがって人間とは、苦痛と退屈のあいだをつねに振り子のように揺れ動く生き物であるといえる」