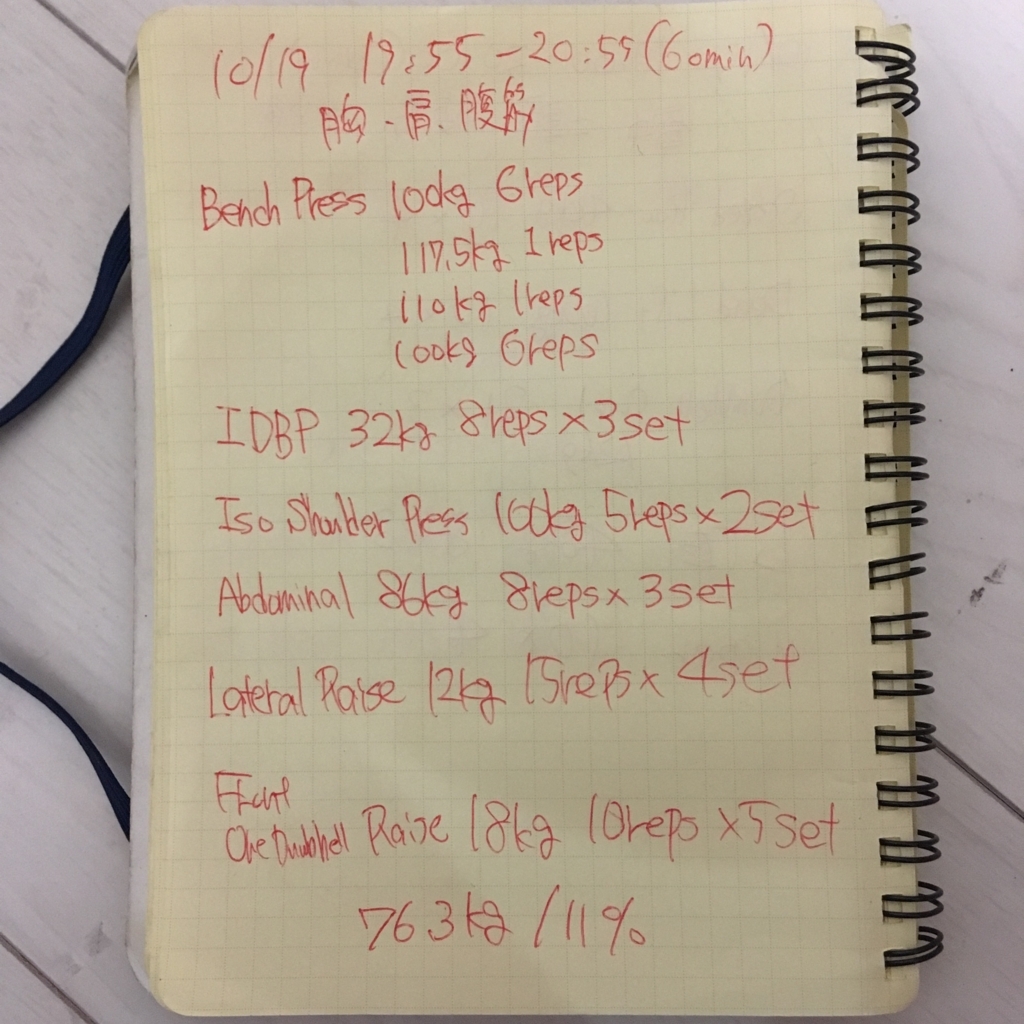「面白かった本ランキング2017年版」暫定1位。
「サピエンス全史」
めちゃくちゃ面白かった。
それもそのはず。
「サピエンス全史」は2016年のビジネス書大賞に輝いた一冊なのだ。
まずはこちらの文章を読んでいただきたい。
今からおよそ一三五億年前、いわゆる「ビッグバン」によって、物質、エネルギー、時間、空間が誕生した。
私たちの宇宙の根本を成すこれらの要素の物語を「物理学」という。物質とエネルギーは、この世に現れてから三〇万年ほど後に融合し始め、原子と呼ばれる複雑な構造体を成し、やがてその原子が結合して分子ができた。
原子と分子とそれらの相互作用の物語を「化学」という。およそ三八億年前、地球と呼ばれる惑星の上で特定の分子が結合し、格別大きく入り組んだ構造体、すなわち有機体(生物)を形作った。
有機体の物語を「生物学」という。そしておよそ七万年前、ホモ・サピエンスという種に属する生き物が、なおさら精巧な構造体、すなわち文化を形成し始めた。
そうした人間文化のその後の発展を「歴史」という。歴史の道筋は、三つの重要な革命が決めた。
約七万年前に歴史を始動させた認知革命、
約一万二〇〇〇年前に歴史の流れを加速させた農業革命、
そしてわずか五〇〇年前に始まった科学革命だ。三つ目の科学革命は、歴史に終止符を打ち、何かまったく異なる展開を引き起こす可能性が十分ある。
本書ではこれら三つの革命が、人類をはじめ、この地上の生きとし生けるものにどのような影響を与えてきたのかという物語を綴っていく。
かっけぇ。。。
高校生の時にこんな本を読んでいれば、
物理や化学をもっと深く理解した上で勉強できただろうなと思う。
「なぜ生きているのか」
「自分は一回きりの人生において何をすべきなのか」
そんな問いを解決する一助になる本だと僕は思う。
- 利己的な遺伝子
- サピエンス全史
この2冊は、視野が広がるので、
めちゃくちゃおすすめ。
これからも「おすすめの本」を問われたらこの2冊は必ず紹介する。
それくらいおすすめ。
「進化論」が好きなのかもしれない。
サピエンス全史(上)メモ
進化が大きな脳を選択するというのは、わざわざ脳を働かせなくてもわかることに思えるかもしれない。
私たちは自分の高い知能に酔いしれているので、脳については、大きいにこしたことはないはずだと思い込んでいる。だが、もしそれが正しければ、ネコ科でも微分や積分のできる動物が誕生していただろう。
動物界広しといえども、ホモ属だけがこれほど大きな思考装置を持つに至ったのはなぜなのか?
じつのところ、大きな脳は、体に大きな消耗を強いる。
そもそも、持ち歩くのが大変で、しかも頭蓋骨という大きなケースに収めておかなければならないのだからなおさらだ。
そのうえ燃費も悪い。ホモ・サピエンスでは、脳は体重の二~三パーセントを占めるだけだが、持ち主がじっとしているときには、体の消費エネルギーの二五パーセントを使う。
これとは対照的に、ヒト以外の霊長類の脳は、安静時には体の消費エネルギーの八パーセントしか必要としない。
女性はさらに代償が大きかった。
直立歩行するには腰回りを細める必要があったので、産道が狭まった──よりによって、赤ん坊の頭がしだいに大きくなっているときに。
女性は出産にあたって命の危険にさらされる羽目になった。赤ん坊の脳と頭がまだ比較的小さく柔軟な、早い段階で出産した女性のほうが、無事に生き長らえてさらに子供を産む率が高かった。
その結果、自然選択によって早期の出産が優遇された。
そして実際、他の動物と比べて人間は、生命の維持に必要なシステムの多くが未発達な、未熟な段階で生まれる。
子馬は誕生後間もなく駆け回れる。
子猫は生後数週間で母親のもとを離れ、単独で食べ物を探し回る。それに引き換え、ヒトの赤ん坊は自分では何もできず、何年にもわたって年長者に頼り、食物や保護、教育を与えてもらう必要がある。
直立歩行へと人間が進化したことで、
人間の子は未熟な状態で生まれるようになった。
虚構、すなわち架空の事物について語るこの能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異彩を放っている。
私たちとチンパンジーとの真の違いは、多数の個体や家族、集団を結びつける神話という接着剤だ。
この接着剤こそが、私たちを万物の支配者に仕立てたのだ。
虚構、神話。
このような概念が人間と他の動物との決定的な違い。
そのような社会構造は空想上のユートピアではない。
動物、とくに私たちに最も近い親戚であるチンパンジーとボノボの間で、詳細に記録されている。
現代の人類の文化でも、たとえばベネズエラの先住民バリ族のもののように、集団的父権制が取られているものは多い。
そのような社会では、子供は単一の男性の精子からではなく、女性の子宮にたまった精子から生まれると信じられている。良い母親はなるべく複数の男性と性交するようにする。
妊娠中はなおさらだ。
そうすれば、自分の子供は最も腕の良い猟師だけでなく、最も優れた語り部や、最強の戦士、いちばん思いやりのある恋人の素質(と、彼らによる世話)を享受できるからだ。これが馬鹿らしく思えたら、心に留めておいてほしい。
近代的な発生学が発展するまでは、赤ん坊がいつも多数ではなく単数の父親によって母親の胎内に宿るという確証はなかったのだ。この「古代コミューン」説の支持者によれば、大人も子供も苦しむ多種多様な心理的コンプレックスはもとより、現代の結婚生活の特徴である頻繁な不倫や、高い離婚率はみな、私たちが自分の生物学的ソフトウェアとは相容れない、核家族と一夫一婦の関係の中で生きるように強制された結果だという。
一夫一妻などという制度は、人間の生物学的ソフトウェアとは根本的に相入れないものであり、浮気や不倫が起こるのは当たり前のことである。
遺伝子レベルで相入れないものなのだから。
では、農業革命はなぜオーストラリアやアラスカや南アフリカではなく、中東と中国と中央アメリカで勃発したのか?
その理由は単純で、ほとんどの動植物種は家畜化や栽培化ができないからだ。
サピエンスは美味しいトリュフを掘り出したり、ケナガマンモスを狩ったりすることはできたが、その栽培化や家畜化は問題外だった。
菌類はあまりに捕らえにくく、巨獣はあまりに獰猛だった。
私たちの祖先が狩猟採集した何千もの種のうち、農耕や牧畜の候補として適したものはほんのわずかしかなかった。
それらは特定の地域に生息しており、そこが農業革命の舞台となったのだ。
人類は農業革命によって、手に入る食糧の総量をたしかに増やすことはできたが、食糧の増加は、より良い食生活や、より長い余暇には結びつかなかった。
むしろ、人口爆発と飽食のエリート層の誕生につながった。
平均的な農耕民は、平均的な狩猟採集民よりも苦労して働いたのに、見返りに得られる食べ物は劣っていた。
農業革命は、史上最大の詐欺だったのだ(2)。では、それは誰の責任だったのか?
王のせいでもなければ、聖職者や商人のせいでもない。
犯人は、小麦、稲、ジャガイモなどの、一握りの植物種だった。ホモ・サピエンスがそれらを栽培化したのではなく、逆にホモ・サピエンスがそれらに家畜化されたのだ。
ここで小麦の立場から農業革命について少し考えてほしい。
一万年前、小麦はただの野生の草にすぎず、中東の狭い範囲に生える、多くの植物の一つだった。
ところがほんの数千年のうちに、突然小麦は世界中で生育するまでになった。生存と繁殖という、進化の基本的基準に照らすと、小麦は植物のうちでも地球の歴史上で指折りの成功を収めた。
一万年前には北アメリカの大草原地帯グレートプレーンズのような地域には小麦は一本も生えていなかったが、今日そこでは何百キロメートルも歩いても他の植物はいっさい目に入らないことがある。
世界全体では、小麦は二二五万平方キロメートルの地表を覆っており、これは、日本の面積の約六倍に相当する。
この草は、取るに足りないものから至る所に存在するものへと、どうやって変わったのか?
歴史の数少ない鉄則の一つに、贅沢品は必需品となり、新たな義務を生じさせる、というものがある。
人々は、ある贅沢品にいったん慣れてしまうと、それを当たり前と思うようになる。そのうち、それに頼り始める。
そしてついには、それなしでは生きられなくなる。
とはいえ、ヒツジ飼いではなくヒツジたちの視点に立てば、家畜化された動物の大多数にとって、農業革命は恐ろしい大惨事だったという印象は免れない。
彼らの進化上の「成功」は無意味だ。
絶滅の瀬戸際にある珍しい野生のサイのほうが、肉汁たっぷりのステーキを人間が得るために小さな箱に押し込められ、太らされて短い生涯を終える牛よりも、おそらく満足しているだろう。
満足しているサイは、自分が絶滅を待つ数少ない生き残りだからといって、その満足感に水を差されるわけではない。そして、牛という種の数の上での成功は、個々の牛が味わう苦しみにとっては、何の慰めにもならない。
進化上の成功と個々の苦しみとのこの乖離は、私たちが農業革命から引き出しうる教訓のうちで最も重要かもしれない。
ロマン主義は、人間としての自分の潜在能力を最大限発揮するには、できるかぎり多くの異なる経験をしなくてはならない、と私たちに命じる。
自らの束縛を解いて多種多様な感情を味わい、さまざまな人間関係を試し、慣れ親しんだものとは異なるものを食べ、違う様式の音楽を鑑賞できるようにならなくてはならないのだ。
これらすべてを一挙に行なうには、決まりきった日常生活から脱出して、お馴染みの状況を後にし、遠方の土地に旅するのが一番で、そうした土地では、他の人々の文化や匂い、味、規範を「経験」することができる
「新しい経験によって目を開かれ、人生が変わった」というロマン主義の神話を、私たちは何度となく耳にする。
農業革命以降、人間社会はしだいに大きく複雑になり、社会秩序を維持している想像上の構造体も精巧になっていった。
神話と虚構のおかげで、人々はほとんど誕生の瞬間から、特定の方法で考え、特定の標準に従って行動し、特定のものを望み、特定の規則を守ることを習慣づけられた。
こうして彼らは人工的な本能を生み出し、そのおかげで厖大な数の見ず知らずの人どうしが効果的に協力できるようになった。
この人工的な本能のネットワークのことを「文化」という。
ホモ・サピエンスは、人々は「私たち」と「彼ら」の二つに分けられると考えるように進化した。
「私たち」というのは、自分が何者であれ、すぐ身の回りにいる人の集団で、「彼ら」はそれ以外の人全員を指した。じつのところ、自分が属する種全体の利益に導かれている社会的な動物はいない。
チンパンジーという種の利益を気にかけるチンパンジーはいないし、グローバルなカタツムリ社会のことを思って骨を折るカタツムリもいないし、全ライオンの王になろうと努力するライオンのアルファオスもいないし、どのミツバチの巣の入口を見ても、「世界の働きバチ諸君、結束しよう!」などというスローガンが掲げられていることはない。だが認知革命を境に、ホモ・サピエンスはこの点でしだいに例外的な存在になっていった。
人々は、見ず知らずの人と日頃から協力し始めた。
彼らを「兄弟」や「友人」と想像してのことだ。
だが、この「兄弟関係」は普遍的なものではなかった。
どこか隣の谷には、あるいは山脈の向こうには、相変わらず「彼ら」の存在を感じられた。最古のファラオであるメネスが紀元前三〇〇〇年ごろにエジプトを統一したとき、エジプトには国境があって、その向こうには「野蛮人」が潜んでいることは、エジプト人たちには明らかだった。
野蛮人はよそ者で、脅威であり、エジプト人が望んでいる土地あるいは天然資源をどれだけ持っているかに応じてのみ、関心を惹いた。
人々が生み出した想像上の秩序はすべて、人類のかなりの部分を無視する傾向にあった。
紀元前一〇〇〇年紀に普遍的な秩序となる可能性を持ったものが三つ登場し、その信奉者たちは初めて、一組の法則に支配された単一の集団として全世界と全人類を想像することができた。
誰もが「私たち」になった。
実際、今日でさえ、硬貨と紙幣は貨幣の形態としては少数派だ。
二〇〇六年に全世界の貨幣は合計約四七三兆ドルだったが、硬貨と紙幣の総額は四七兆ドルに満たない(7)。
貨幣の合計の九割以上(私たちの会計簿に記載されている四〇〇兆ドル以上)は、コンピューターのサーバー上にだけ存在する。
したがって、商取引のほとんどは、有形の現金のやりとりをまったく経ず、一つのコンピューターファイルから別のコンピューターファイルへと電子データを移動させることで行なわれる。
たとえば、札束の詰まったスーツケースを渡して家を買うのは犯罪者ぐらいのものだ。
人々が電子データとの交換で品物やサービスの売買を進んで行なうかぎり、そのほうがピカピカの硬貨や手の切れそうな紙幣よりも、なお便利だ。
軽くて、かさばらず、動向を追いやすい。
つまり、貨幣は物質的現実ではなく、心理的概念なのだ。貨幣は物質を心に転換することで機能する。
人々が進んでそういうことをするのは、自分たちの集合的想像の産物を、彼らが信頼しているときだ。
信頼こそ、あらゆる種類の貨幣を生み出す際の原材料にほかならない。
したがって、貨幣は相互信頼の制度であり、しかも、ただの相互信頼の制度ではない。
これまで考案されたもののうちで、貨幣は最も普遍的で、最も効率的な相互信頼の制度なのだ。
哲学者や思想家や預言者たちは何千年にもわたって、貨幣に汚名を着せ、お金のことを諸悪の根源と呼んできた。
それは当たっているのかもしれないが、貨幣は人類の寛容性の極みでもある。
貨幣は言語や国家の法律、文化の規準、宗教的信仰、社会習慣よりも心が広い。
貨幣は人間が生み出した信頼制度のうち、ほぼどんな文化の間の溝をも埋め、宗教や性別、人種、年齢、性的指向に基づいて差別することのない唯一のものだ。貨幣のおかげで、見ず知らずで信頼し合っていない人どうしでも、効果的に協力できる。
貨幣の代償 貨幣は二つの普遍的原理に基づいている。
a 普遍的転換性──貨幣は錬金術師のように、土地を忠誠に、正義を健康に、暴力を知識に転換できる。
b 普遍的信頼性──貨幣は仲介者として、どんな事業においてもどんな人どうしでも協力できるようにする。
私たちの眼前で生み出されつつあるグローバル帝国は、特定の国家あるいは民族集団によって統治されはしない。
この帝国は後期のローマ帝国とよく似て、多民族のエリート層に支配され、共通の文化と共通の利益によってまとまっている。世界中で、しだいに多くの起業家やエンジニア、専門家、学者、法律家、管理者が、この帝国に参加するようにという呼びかけを受けている。
彼らはこの帝国の呼びかけに応じるか、それとも自分の国家と民族に忠誠を尽くし続けるか、じっくり考えなければならない。
だが、帝国を選ぶ人は、増加の一途をたどっている。